2005/10/21
時差のせいか朝早く目がさめてしまいます。学会は朝6時半からです。フロアにおいてある朝食をとって、ポスターを見てまわります。
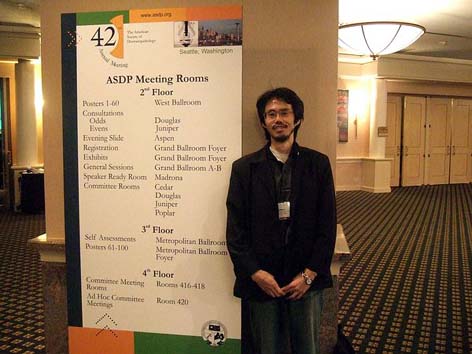 ASDPポスターの前で
ASDPポスターの前で |
8時からShort Course Iを聴講。これは、Neglected topics in Dermatopathologyというタイトルで、熱帯地方の皮膚病理、爪の皮膚病理、色素異常の皮膚病理、組織球症の4つの講演でした。Tropical
Dermatopathologyは主にMycobacteriosisについて症例紹介の形の講演でした。爪の話は、爪は見なれないので難しいという話ではじまって、生検のし方、検体の取り扱い、解剖、そして、感染症、炎症性疾患、色素性病変と盛り沢山でした。最後のほうは時間が足りなくなりました。この講演は、UCSFのRuben先生がしたのですが、爪の色素細胞性母斑の症例が、私達が、UCSFのLeBoit
先生にコンサルテーションした症例のようで、ちょっと嬉しくなりました。色素異常の話はLeBoit 先生が総論的に話されました。Histiocytosisの話はGlusac先生が症例を提示して考えていくというスタイルでLangerhans
cell histiocytosis, congenital self healing histiocytosis, Juvenile
xanthogranuloma, Multicentric reticulohistiocytosis, Reticulohistiocyotma,
Xanthoma disseminatum, Benign cephalic histiocytosis, Rosai-Dorfman
disease, Leprosy, Epithelioid cell histiocytosisなどを紹介されました。
Box lunch(でかい!) のサンドイッチをもらって、Oral sessionを聞きます。たとえば、NKI/C3はCellular
neurothekeomaのマーカーとして知られているが、調べてみるといろいろな腫瘍や正常組織でも発現されるので特異性は低い、とか、Syringomatous
adenoma of the nippleとMicrocystic adnexal carcinomaはHE染色では非常に類似しているが、免疫染色では異なったマーカーを発現し、異なった腫瘍である、とか、FXIIIaはどの程度有用なのか、など皮膚の診断病理にとって面白い話がたくさんありました。
14:30からはElson B. helwig Memorial Lectureで、先日電顕皮膚生物学会で札幌にもこられた、Graz大学のLorenzo
Cerroni先生のlymphomaの講演を聞きました。
15:30からは最初のPoster defenceセッションです。質問をしようと思っていたポスターのところへ行きましたが、演者は不在。結構、その場にいない先生も多いようです。
夜はPresident's Reception & Banquetがあるのですが、今回はパスしました。食事をしてホテルで休んでから、Slide
libraryへ。教育的な症例100例を順に見ていきます。この日は1/3くらい見ました。ポスターもこのとき貼りました。
|